新人として新しい職場に入った時、誰もがぶつかる壁があります。それは「質問の仕方」です。
「これ、どうすればいいですか?」と聞くべきか。 「こんな簡単なことを聞いて、嫌われないだろうか?」と躊躇すべきか。 「先輩は忙しそうだけど、いつ話しかければいいんだろう?」とタイミングに悩むか。
私もかつて、この「質問の壁」に何度も頭を打ちつけました。
しかし、37歳になり、中小電機メーカーから一部上場の同業他社へ転職し、営業一筋で20年近くキャリアを積んだ今、断言できることがあります。それは、質問の仕方は、単なる業務遂行の手段ではないということです。
質問の仕方は、あなたの「仕事への姿勢」「自己成長への意欲」、そして「コミュニケーション能力」そのものとして、先輩や上司に評価されています。質問の「質」が上がれば、あなたの評価は上がり、職場の人間関係は円滑になり、結果として仕事はスムーズに進みます。
このブログ記事では、私自身が新人時代に犯した痛い失敗談と、中堅・ベテランになってから実践し、効果を実感した成功例を、記事の約半分を割いてご紹介します。
誰もがぶつかる悩みを解決し、あなたの職場での評価を一段階引き上げるための、実践的な「質問のコツ」を、実例を交えて徹底的に解説します。
質問のコツ:理論編 – 準備と基本動作
まずは、質問をする前に必ず押さえておくべき、基本的な「型」から解説します。この「型」を身につけるだけで、あなたの質問は劇的に改善します。
コツ1: 質問前の「自己解決の努力」を可視化する
最も避けたい質問は、「これ、どうすればいいですか?」という、丸投げ型の質問です。
先輩が最もストレスを感じるのは、「この新人は、何も考えずに聞いてきたな」と感じる瞬間です。質問の目的は、先輩の時間を奪うことではなく、自分の努力では解決できなかった最後の壁を乗り越えることにあるべきです。
だからこそ、質問をする際には、必ず「質問に至るまでのプロセス」をセットで伝える必要があります。
| 質問のNG例 | 質問のOK例 |
| 「この資料の作成方法が分かりません。」 | 「この資料について、過去の類似資料(AとB)を参考に、Cという構成案を作成しました。しかし、データソースDの取得方法が分からず、先に進めません。Dの取得方法についてご教示いただけますでしょうか?」 |
| 「システムのエラーが出ました。」 | 「システムのエラーコードEが出ました。マニュアルFを確認したところ、原因はGの可能性が高いと書かれていました。Gの対応策としてHを試しましたが、解決しませんでした。他に確認すべき点、または試すべき対応策はありますでしょうか?」 |
このように、「調べたこと」「試したこと」「自分なりの仮説」を先に提示することで、先輩はあなたの努力を認め、どこからアドバイスを始めれば良いかを瞬時に判断できます。
これは、単に答えを聞き出すだけでなく、「私はここまで考えました」というあなたの能力をアピールする絶好の機会にもなるのです。
コツ2: メモは「記録」ではなく「対話の準備」
「メモを取る」ことは、新人の基本動作として教えられますが、その目的を履き違えている人が非常に多いと感じます。
メモは、「先輩の回答を漏らさず記録すること」だけが目的ではありません。真の目的は、「質問の質を高め、二度手間を防ぐこと」、そして「先輩に安心感を与えること」です。
質問前のメモの準備
質問をする前に、以下の3点を必ずメモに整理しておきましょう。
1.質問の要点(ゴール): 「何を知りたいのか」を1文でまとめる。
2.現状と仮説: 「どこまでやったか」「なぜ行き詰まったか」「自分はどう考えているか」を箇条書きにする。
3.回答の記入スペース: 先輩の回答を書き込むスペースを空けておく。
このメモを先輩に見せながら質問することで、「この新人は、質問の整理ができている」という印象を与えられます。
コツ3: 質問は「時間帯」と「場所」を選ぶ
どれだけ質問の質が高くても、タイミングが悪ければ先輩の機嫌を損ねてしまいます。
避けるべき時間帯
•始業直後: メールチェックや一日のタスク整理で集中している時間帯です。
•終業間際: 帰宅準備や残務整理で焦っている時間帯です。
•会議直前: 集中力を高めている、または資料の最終確認をしている時間帯です。
ベストなタイミングの見極め方
先輩がパソコンから少し目を離した瞬間、コーヒーを飲んでいる瞬間など、「作業の区切り」を見計らいましょう。
そして、話しかける際には、必ず「今、5分ほどお時間よろしいでしょうか?」と、必要な時間を明確に伝えることが重要です。これにより、先輩は自分のタスクとの兼ね合いを判断しやすくなります。
また、質問の内容が機密性の高いものであれば、席を立って会議室や給湯室など、周囲に聞かれない場所を選ぶ配慮も必要です。
筆者の失敗と成功:体験談編
ここからは、37歳の私が、社会人生活で実際に経験した「質問」にまつわる失敗と成功のストーリーを、赤裸々にご紹介します。
体験談1: 「メモ魔」が嫌われた新人時代(22歳〜25歳)
新卒で入社した中小電機メーカーでの営業職時代の話です。私は真面目な性格だったので、「先輩の話はすべてメモを取れ」という教えを忠実に守っていました。
質問をするたびに、先輩の言葉を一言一句逃すまいと、必死にメモを取ります。しかし、先輩からの評価は最悪でした。
ある日、プロジェクトリーダーのA先輩に、同じシステムの操作方法について3度目の質問をしたときのことです。A先輩は、私のメモ帳を指さして、静かにこう言いました。
「君のメモは、ただの『記録』。そこに書いてあることを、君は理解していない。君は質問の前に、自分で何も調べていないからだ。メモを取ることに満足して、『分かったつもり』になっているだけだ。次に同じことを聞いたら、そのメモを破り捨てるぞ。」
この言葉は、当時の私にとって強烈なショックでした。私は、メモを取るという「行動」で、「考えること」をサボっていたのです。
教訓: メモは手段であり、目的ではありません。重要なのは、メモに書かれた内容を「自分の言葉で再現できるか」、そして「次に同じ問題に直面したときに、そのメモを見て解決できるか」という「再現性」です。この失敗から、私は質問の前に必ず「このメモだけで、次に一人でできるか?」と自問するようになりました。
体験談2: 「仮説の提示」で評価が一変した瞬間(28歳〜32歳)
入社6年目、私は中小電機メーカーの営業として、大型案件の顧客データ管理を任されていました。しかし、顧客情報と過去の取引履歴を照合する際、どうしても数値が合わないという問題に直面しました。締め切りは翌日。私は焦りながらも、新人時代の失敗を思い出し、まずは自分で徹底的に調べることにしました。
•試したこと: 顧客管理システム(CRM)の操作ログ確認、過去の類似案件のデータ構造分析、社内規定の確認。
•行き詰まり: ログを比較しても、原因となる操作の違いが見つからない。
•仮説: 3時間格闘した結果、私は以下の3つの仮説を立てました。
•仮説A: 顧客情報の入力担当者が、部署異動の情報を古いシステムに入力し続けている。
•仮説B: 過去の取引履歴データが、最新の会計システムと連携できていない。
•仮説C: そもそも、私が参照すべき「取引履歴」の定義が、社内と部署で異なっている。
私は、このメモを持って、営業部長のB先輩の席へ向かいました。
私: 「B部長、今、5分だけお時間よろしいでしょうか?大型案件の顧客データ照合で数値が合わず、ご相談させてください。」私: 「3時間ほど調べた結果、A、B、Cの3つの仮説を立てました。AとBは、システムログと会計データから可能性が低いと判断しています。仮説C、つまり『私が参照すべき取引履歴の定義が異なっている』という可能性が最も高いと考えているのですが、この案件で参照すべき『正式な取引履歴』は、どの部署のどのデータになりますでしょうか?」
B部長は、私のメモを一瞥し、すぐに答えました。
B部長: 「ああ、その案件はね、特殊でね。販売部門のデータじゃなくて、財務部門の『売掛金管理台帳』を参照するのが正解なんだ。君の仮説Cが正解だ。そこまで考えているなら、あとは財務に確認するだけだね。よく調べた。」
この瞬間、私は質問の「質」が評価されることを肌で感じました。先輩は、私が3時間かけて考えたプロセスを瞬時に理解し、最も効率的な回答をくれました。この一件以来、B先輩は私を信頼し、重要な仕事を任せてくれるようになりました。
教訓: 質問は、「答えを聞く行為」ではなく、「自分の思考プロセスを検証してもらう行為」です。仮説を立てることで、先輩はあなたの能力を評価し、信頼を寄せてくれるようになります。
体験談3: 質問を「予約」するテクニック(37歳・教える側として)
現在、私は一部上場の同業他社に転職し、営業チームのリーダーとして、新人の指導も担当しています。そこで、私が実践し、新人にも教えているのが、「質問の予約」というテクニックです。
新人は、先輩が忙しそうにしていると、遠慮して質問を溜め込みがちです。しかし、溜め込んだ質問は、いざ質問する時に先輩の時間を大量に奪うことになります。
そこで、私は新人に対し、「質問は小出しに、そして予約せよ」と教えています。
質問予約の実例
ある新人C君は、私が集中して作業しているのを見て、こう話しかけてきました。
C君: 「リーダー、今、手が離せない状況かと思いますので、後ほどで構いません。5分で終わる質問が3点あります。今日の15時か、明日の午前中で、5分だけお時間をいただけませんか?」
これを聞いた私は、心の中で「よし!」と思いました。
1.「5分で終わる質問が3点」: 質問の量と必要な時間が明確。心理的な負担が非常に軽い。
2.「今日の15時か、明日の午前中」: 選択肢を提示することで、私の都合を尊重してくれている。
私はすぐに「じゃあ、15時に声かけて」と答え、自分の作業を中断することなく、C君の質問に答える時間を確保できました。
教訓: 忙しい先輩にとって、最も負担なのは「いつ終わるか分からない質問」です。質問の量と時間を明確に伝え、先輩に「質問を受ける準備」をさせることで、先輩の心理的負担を軽減し、快く質問に答えてもらえる環境を作ることができます。
体験談4: 質問の「クローズ」を意識する
質問が終わった後、あなたはすぐに自分の席に戻っていませんか?
質問の最後には、必ず「質問のクローズ(完了)」を行う必要があります。これは、先輩との認識のズレを防ぎ、先輩に「この質問は完全に終わった」という安心感を与えるための、非常に重要なステップです。
質問クローズの実例
先輩から回答をもらった後、私は必ず以下のフレーズで締めくくるようにしています。
私: 「ありがとうございます。承知いたしました。つまり、この件は〇〇という認識で進めます。もし、この認識で問題があれば、すぐにフィードバックをいただけますでしょうか?」
このように、回答を自分の言葉で要約し、先輩に確認を取ることで、以下の効果が生まれます。
1.認識のズレ防止: もし要約が間違っていれば、先輩はその場で訂正してくれます。
2.安心感の提供: 先輩は、あなたが正しく理解したことを確認でき、安心して自分の作業に戻れます。
3.責任の明確化: 「この認識で進めます」と宣言することで、その後の作業に対する責任感を先輩に示すことができます。
教訓: 質問は、回答をもらって終わりではありません。「理解したことの確認」まで含めて、一つの質問プロセスです。このクローズを徹底することで、あなたの仕事の正確性が向上し、先輩からの信頼は揺るぎないものになります。
まとめ:質問上手は仕事上手
ここまで、私が20年近い社会人経験で培ってきた「先輩に好かれる質問のコツ」を、理論と実例を交えてご紹介しました。
質問のコツをまとめると、以下の3点に集約されます。
1.質問前の準備: 「調べたこと」「試したこと」「仮説」を明確にし、自己解決の努力を可視化する。
2.相手への配慮: 質問のタイミング、場所、そして必要な時間を明確に伝え、先輩の負担を最小限にする。
3.質問のクローズ: 回答を自分の言葉で要約し、認識のズレがないか確認する。
質問は、あなたの「自己成長への意欲」と「相手への配慮」を示す、最高のコミュニケーションツールです。
質問を恐れる必要はありません。しかし、雑に扱ってはいけません。
今日から、質問の「型」を意識し、先輩の時間を大切にする質問を心がけてみてください。きっと、あなたの職場での評価は上がり、仕事はより楽しく、スムーズに進むようになるはずです。
質問上手は、間違いなく仕事上手です。あなたの活躍を心から応援しています。
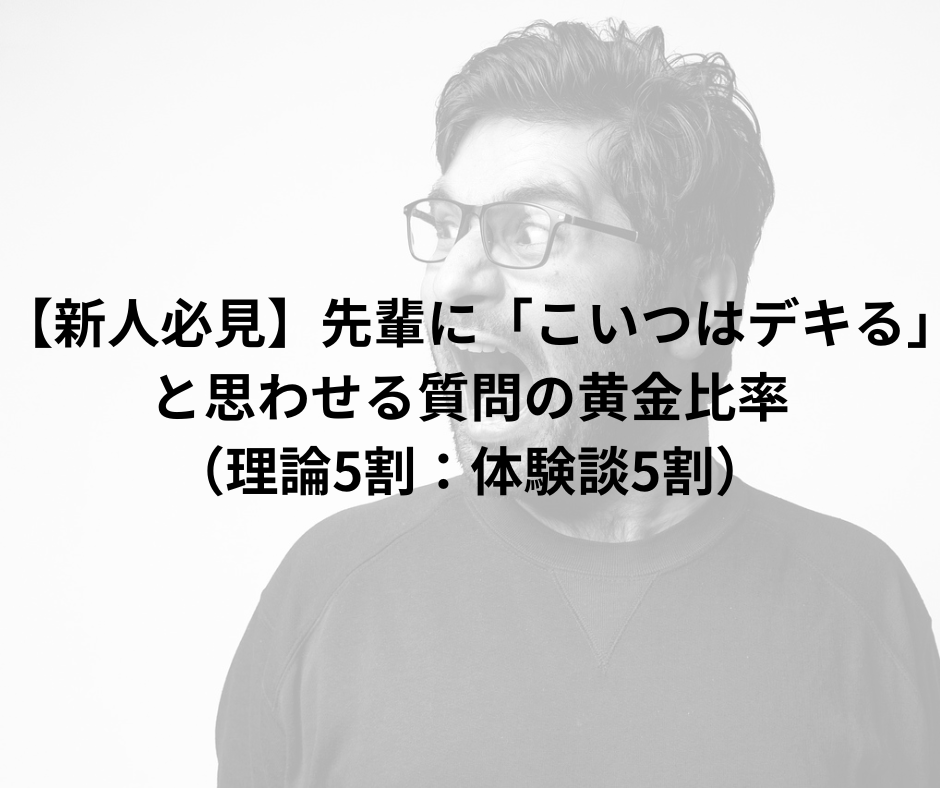
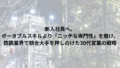
コメント